先日の東北地区歯科医学会でもありましたが
歯の溝には歯ブラシの毛先が届かないため、フッ素塗布やフッ素洗口が有効なのです。
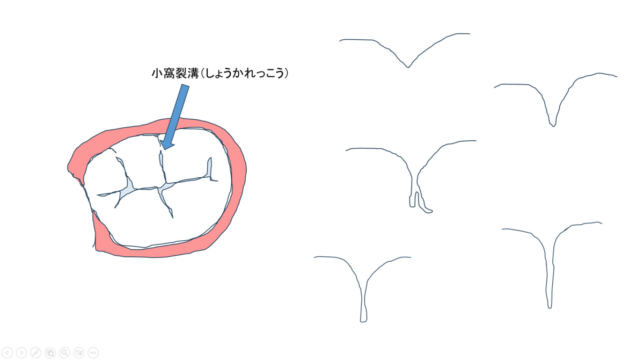
浅い溝、深い溝、複雑に分岐した深い溝、
途中ですぼんで中で広がる溝と個人によって形状は様々です。
裂溝の幅は20ミクロン(0.02ミリ)程で、歯ブラシの毛先の直径は0.2ミリ程です。
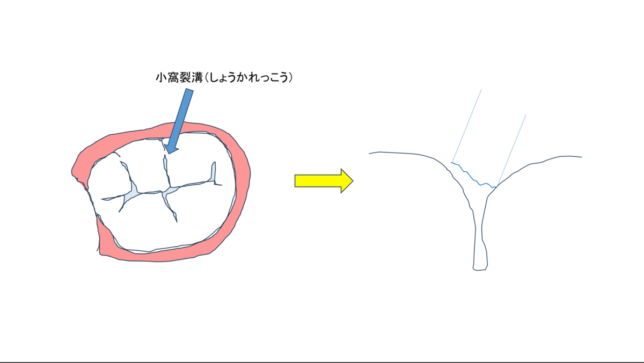
顕微鏡レベルで見た場合をイメージするとこんなイメージ。
溝の形状によっては、これではどうやっても歯ブラシの毛先が届かないのです。
歯磨きを正しく適切にすることが基本ですが
歯磨きだけでのむし歯予防には限界があります。
そのため歯科医院での口腔ケア、フッ素塗布、フッ素洗口の併用が重要なのです。
また歯肉炎、歯周病予防には歯垢除去が重要なので
歯みがきが重要であることに変わりありません。



